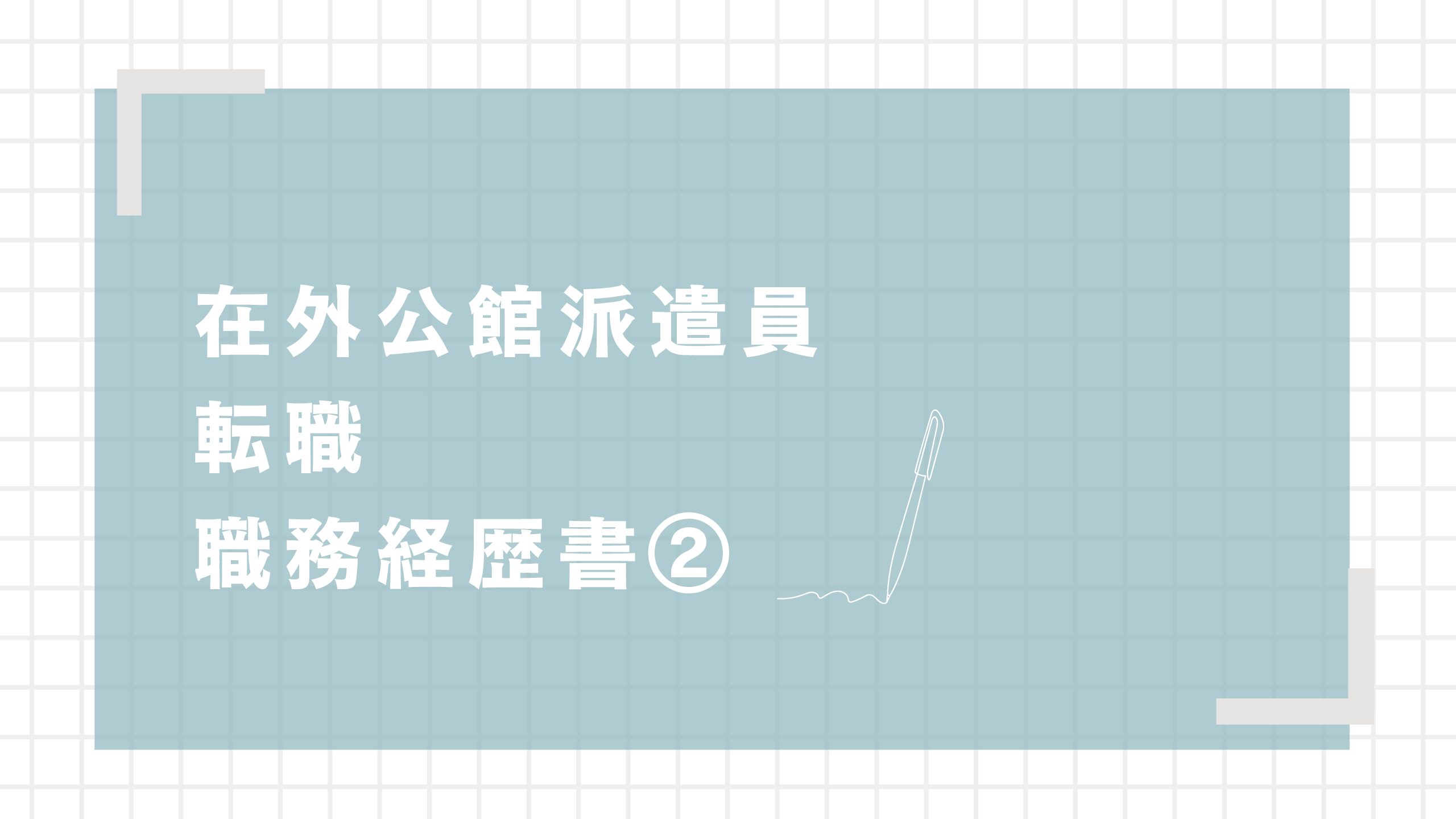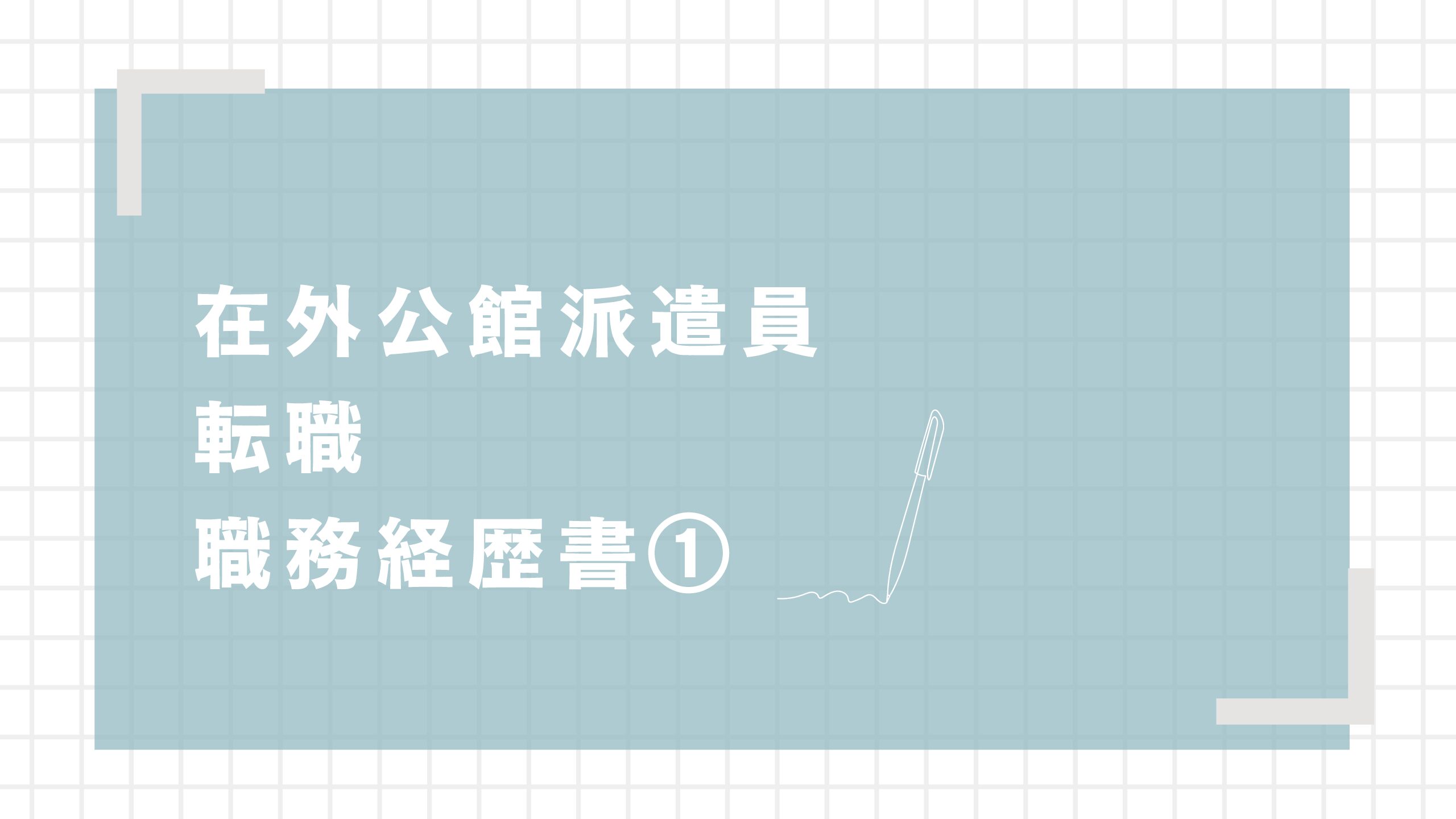【ポイント】
- 職務経歴書は経験した組織が~1社である場合は1枚以内
- 各構成要素には字数制限あり。インプレッションを大切にするため必ず遵守する
職務経歴書の書き方①│ダメな職歴書とは?見本とともに解説の続きです。この記事では、実際に用いるべき職務経歴書の雛型を紹介します。完全オリジナル版であり、一発で印象付けることができます。
職務経歴書の見本
以下をご覧ください。職務経歴書の書き方①│ダメな職歴書とは?見本とともに解説で説明した「読みたくない」職務経歴書と比較すると、よりその差が分かると思います。
体裁を整えるだけで全く異なる印象になります。書きぶりや表現については個々の能力に依るところもありますが、少なくとも体裁については雛形に沿えばいいだけなので、誰でも簡単に作業することが来ます。
テンプレートと注意点
雛形のダウンロードに先立ち、注意すべきことが1点あります。
それは、枚数の関係上、経験した社数によって雛形が異なるということです。経験した会社が1社である場合は1枚以内です。2社以上の場合、どんなに経験していても必ず2枚以内に収めるようにします。
職務経歴書は3枚以上でも可とする転職サイトもありますが、1枚めくってさらにもう一枚or一回のスクロールで下まで辿り着けない時点で読む気は削がれます。どんなに多くても2枚が限界です。
ここでは最大4社までを想定して雛形を作成しました。それぞれ適切な段組みにしてあるので、ご自身の経験社数に応じて適宜ご活用ください。
作成時の注意点
各項目のポイントです。
職務概要
職務概要とはその名のとおり概要を書く部分です。ポイントは以下の2点です。
基本セットは「Where」 と「 What」
基本的には、「どこで」「何をした」が書けていれば問題ありません。上記の例で言えば、
Where=○○大使館
What=バックオフィス要員として大使館運営の支援。会計、人事、総務関連に従事・・・
例えば経験社数が2社でも同様であり、「1社目は○○社に入社。○○部に配属され、▲▲業務を中心に行う。その後、(社)国際交流サービス協会の在外公館派遣員として○○大使館に派遣され、総務班に所属。出張者受入支援を行う。」といった具合に書きます。
簡単なアピールで〆
職務概要の本来の趣旨に則れば、冒頭見本のような「○○国で駐在し、英語が出来ます」という〆の言葉は無くても問題ありません。
しかし、職務概要は人事が一番最初に目を通す部分です。職務全体を通じて培ったことで、かつ市場価値が高いキーワードは盛り込むとより映えると思います。駐在経験や語学力は価値を見出すことができるため、派遣員経験がある場合には見本の一文をコピペする形でいいでしょう。
また、もし派遣員経験ないものの本記事を参考にして下さっている場合は、例えば「係長として部下〇名の経験有」や「全国営業部門最優秀賞を連続受賞」といった、簡単なアピールを行うと文全体に締まりが出るとともに、これ以降の部分への導入となるでしょう。
ただし、いずれも共通して言えることは、「コミュニケーション力」や「課題解決スキル」などの具体的なワードは避けるべきです(具体的スキルは別項目で記載します)。あくまでも抽象的なワードに留めるようにしてください。
職務経歴
職務経歴のポイントは3つです。
「主な業務内容」は業務種別毎に記載
経験社数が1社のみの場合、「主な業務内容」は6行分書く必要があります。
ここは若干大変な部分でもありますが、自己分析の方法:ステップ1:「振り返り」で自身の業務をリストアップしたことを思い出しながら作業に当ってみてください。
冒頭の例でいえば、「会計補助」「人事補助」「調達」「便宜供与」「配車」「庶務」に分けています。6つに分解することが難しい場合は、これを参考に考えてみるといいでしょう。
「工夫・取組」は自己分析を再利用する
左下のボックス「工夫・取組」は、自己分析の方法:ステップ2:「要素分解」1の内容をそのまま使うことが出来ます。自身の仕事における「困難」と「工夫」を4行で纏めるようにしてください。この欄については、’ですます調’でなくて結構です。
「成果」は定量表現に拘り過ぎない
右下のボックス「成果」の部分ですが、定量表現に拘り過ぎないようにしましょう。
例えば、営業の経験があるのであれば「新規顧客獲得数が前年比で○○%増加した」と言えます。しかし、職種によっては定量的な評価が出来ない場合もあります。
例えば、「工夫・取組」で口上書の発出プロセスを改善しミス減少を達成したとします。これを「ドラフト作成時のミスが○○%減少」と書いてしまうと、鋭い人事であれば「これって本当に計測しているの?」と思うはずです。
事実、定量表現したほうが成果は伝わりやすいものの、無理矢理は避けるべきです。定性表現でも十分伝わりますので、成果の性質に応じて使い分けるようにしましょう。
保有資格
保有資格の欄のおけるポイントです。
ニッチな資格は注意する
IELTSやTOEICの資格、簿記の資格等があれば追記します。修士号を取得している場合は、このスペースに記載します。
注意すべき点として、資格を五月雨式に書くことは避けましょう。実際にあった話ですが、私の友人が務めるメーカー企業で、経理の応募に「世界遺産検定」及び「柔道3段」という記載の職務経歴書が送られてきたことがあるそうです。
例えば、警備の前衛部隊ならば、柔道3段は有益な資格でしょう。また、旅行代理店のツアーコンダクターや営業であれば「世界遺産検定」は関連性が見出せます。
もちろん、書いたところで特段の障害が生じるわけではないものの、逆に書いたところで何か意味があるわけでもありません。
人によっては「書くことがなかったのかな・・・」という、どちらかというマイナスの印象を抱いてしまうケースがあります。リスクを取る必要がないのであれば、ニッチな資格や応募先とあまり関係の無い資格は書かないほうがいいでしょう。
参考までに、以下の資格はどのようなポストでも普遍的なため、保有する場合には記載して下さい。
- 運転免許
- 語学関連の資格
- 修士/博士号
- 士業関連
- 会計関連(簿記/FP等)
- IT関連(MOS/ITパスポート等)
- 他
活かせるスキル・知識
スキルについては、自己分析の方法:ステップ4:「スキル」で選択したスキルを書くようにします。また、語学力についても、派遣員の皆さんなら十分なレベルだと思いますので、該当言語を書いてください。また、特別な知識を有している場合には、その知識を書きましょう。
知識は、経験3年以上が目安
ここでいう知識とは、応募先ポストと親和性があり、かつ相当レベル(目安3年)に達している必要があります。
例えば、国際開発業界に3年間携わったことがあり、今回も関連ポストであるならば、ODA関連知識と書いてもいいと思います。IT企業に応募する予定で、SQLのselect構文をベースにhavingやorderが使いこなせるのであれば、SQL関連知識と書いてもいいでしょう。
他方で、例えばアフリカにいただけでODA関連知識と書いてみたり、学校で経済学の授業を受講しただけで「マクロ経済」と書くことは避けましょう。つまり、突っ込まれた時に説明・回答できる程度でなければ下手に知識を書くことは避け、何らかのスキルで埋め合わせするようにして下さい。
自己PR
自己PRは、自己分析の方法:ステップ3:「自己PR」(テンプレ付き)で作成した内容を引用するようにします。ただし、若干加筆する必要がありますので注意してください。
強み + 自己PR文 + 弱みの改善
職務経歴書で自己PRを記載する際には、まず、最初に強みを一言で言いきります。冒頭例でいえば「私の強みは、「忍耐力」です。」の部分が該当します。
その上で、自己分析の方法:ステップ3:「自己PR」(テンプレ付き)で作成した自己PR文を記載し(てにをは等は修正加筆)、最後に自分の弱みを今後も改善していく姿勢をアピールしましょう。
まとめ
雛形とともに、具体的な書き方について説明しました。ところどころ、第1章自己分析で実施した作業結果を使用する部分もあります。もし本ページを最初に御覧の方は、【必読】自己分析のやり方についても是非ご一読下さい。